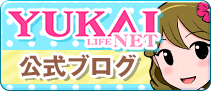ひとみしょう 作 『世界が変わるとき』第1話
―――それは、一人の女性の成長物語―――ユカイノベル
世界が変わるとき ~自分に自信がなかったわたしが自信を持つまで~
ひとみしょう 作
第1話「ピンストライプのパンプス」

「あなた、お買い物が好きでしょう?」
去年見てもらった占い師は、私の名前を見ただけで、そう言い当てた。
山本優子というありふれた名前だけを見て、なぜそう言い当てることができたのか、わたしは今でも不思議に思う。
占い師は続けて、こうも言った。
「お買い物が好きな人は、自分に自信がないのよ。あなたは美人さんなんだから、もっと自分に自信を持ちなさい」
80歳くらいの白髪の占い師は、穏やかな表情でやさしくわたしにそう言って、にっこりと微笑んだ。その落ち着いた口調とやわらかな眼差しがあたたかくて、わたしは今でもこの言葉を覚えている。
たしかに、わたしは買い物が大好きだ。
まだ月初だというのに、今月はすでにルイヴィトンの真っ赤なカバンを買った。イエナスローブのTシャツも、FRAY I.Dのワンピースも買った。LIP SERVICEのピンストライプのパンプスを買うときに、クレジットカードが使えなくて恥ずかしかった。
店員さんは申し訳なさそうな顔をして「お客様、このクレジットカードは使えないようで……何回かカードを機械に通してみたんですが……もういちど通してみましょうか」とわたしに言った。
わたしは「だいじょうぶです、ちょっとそのへんでお金おろしてきますね!」と言って、逃げるように店をあとにした。
だって、カードの限度額めいっぱいに買い物をしている事実を、わたしは他の誰よりもよく知っている。もちろん、わたしの銀行口座に、お金なんてものは入っていない。
それにしても、恥ずかしくってあの店にはもう行けない、と溜息をついた。
どうしてわたしは、こんなに買い物ばかりしてしまうのだろう?
どうしてわたしは25歳にもなって、こうも自分に自信が持てないのだろう?
高校時代からの友だちの梨奈は、いつ電話をしても楽しそうにしゃべるし、その声は自信に溢れているように感じる。そもそも彼女は、自分に自信があるとかないとか、そんなことを考えたことすらないような気さえする。
でも、まあ、しょうがない。
お金がないことをいくら悩んでも、お金は入ってこない。自分に自信がないことを悩んでも、自信を持てるようにはならないのとおなじように。
目黒区にあるひとり暮らしのワンルームマンションに帰ると、クレジットカード会社から請求書が届いていた。しかも4通も。
払えない請求書を見ても、お金は入ってこないしね。
わたしは小さな声でそう言って、請求書をぜんぶ丸めてゴミ箱に投げ捨てた。
ルイヴィトンのカバンからスマホを取り出して、ネットに散乱する求人サイトを眺める。
お金がないのなら、お金を稼げばいい。それも、クレジットカード会社がびっくりするくらいの金額を。LIP SERVICEの1万円するピンストライプのパンプスなんて、10足でも20足でも買えるくらい、お金を稼げばいい。
「求人」と名のつくサイトを回遊するうち、風俗の求人サイトに行きついた。
給料のいいお仕事、というのは漠然と知っていた。でも求人内容をちゃんと読んだのは今回が初めてだ。
……時給にすると、1万円? 2万円? え、そんなに?
色々な求人情報を眺めるうちに、わたしは風俗でバイトをするのも悪くないように思えてきた。不安な部分ももちろんあったけれど、今は体験入店なんてものがあるらしい。少しやってみて向いていなかったら、すぐに退店することもできる。
いちど、試してみるのもいいかも。
ちょっと手や舌でお客さんを喜ばせれば、1万円とか2万円とかが入ってくるのだ。しかもたったの60分くらいで。
Hが嫌いなわけじゃないし、わたしは顔も悪くない。おっぱいだってEカップある。お客さんと楽しく話してちょっとHなことをして……これならわたしにもできるかもしれない。
風俗求人サイトの応募画面を前にして、妙な自信がふつふつと湧いてきたわたしは、ちゃちゃっと歌舞伎町のデリバリー・ヘルスに応募を済ませた。
お金が入ってきたらなにを買おうかなと考えながら、そのへんの床に転がっていたファッション雑誌をぱらぱらとめくりはじめる。
お金も、雑誌をめくるみたいに、ぱらぱらと降ってくればいいのに。
*
歌舞伎町のデリヘルの待機室で、置いてあった女性週刊誌をぱらぱらとめくりながらわたしは、デリヘルの面接って、なんであんなに簡単に終わるのだろうと思った。
面接担当者が仕事の内容や給与(日給5万円保証!)、サービスのシステム(キスあり、フェラあり、シックスナインあり、本番なし、など)を丁寧に説明してくれた。わたしが「入店します」と言うまで、本名も聞かれなかったし、履歴書や身分証の提出も求められなかった。
入店の意思があることを面接担当者に告げ、できれば今日からアルバイトをしたいと言うと、待機室に案内してくれた。
待機室で女性週刊誌を眺めていたら、男子スタッフが、優子さんに初めてのお仕事が入ったので、歌舞伎町の**というホテルに行ってくださいと言われた。
「お客さんのなかには、風俗業界未経験の女の子が大好きという人もいて、電話で女の子のプロフィールを紹介するだけで指名が入ることもあるんですよ、優しい常連さんだから緊張しなくて大丈夫ですよ」
ホテルは待機所から歩いてすぐのところだったけれど、スタッフは丁寧にその場所を説明してくれた。
男子スタッフに「緊張しなくても大丈夫」と言われても、これから見ず知らずの男の人にハダカを見られるんだという不安や恐怖はもちろん消えなかった。
よく買い物に来ていた新宿のマルイやルミネがすぐそばにあるのに、今わたしが歩いている歌舞伎町の街は、まったく知らない街のように見えた。そもそもわたしのことを指名してくれたお客さんって、どんな人?
それでも、梅雨明け間近の歌舞伎町の空気を胸いっぱいに吸うと、少し気持ちは落ち着いてきた。
「面接担当の人は、女子大生で風俗バイトをしている子も多いって言ってたし、大丈夫でしょ!」とわたしは自分をはげましながら、ホテルを目指した。
指定されたホテルの部屋に入って、緊張から戸惑っていると、お客さんのほうからたくさん話しかけてきてくれた。遊び慣れていそうな、でも女子への気遣いに長けている感じの、40歳くらいの男性だった。
彼は、これからなにをすればスムーズに事が運ぶのか、なにをやったら女の子に嫌われるのかなど、すべてを知っているのかのように、会話によどみがなく、行動に無駄がなかった。しかもわたしが緊張しないように、会話の途中にいくつかのギャグを混ぜてくれた(そのうちの半分くらいのギャグはすべっていた)。
少ししたら彼は「お金はそこに置いておいたから、ちょっと金額を確認して」と言った。
わたしはお礼を言い、彼がベッド脇のサイドテーブルの上に用意してくれていた封筒を開ける。ちょうど3万円あった。90分で3万円。もういちど彼にお礼を言ってから、その封筒をカバンにしまった。
90分で3万円、女の子の取り分が2万円。料金の話は前もって聞いていたけれど、にわかには信じがたかった。こうして受けとった今も現実感があまりない。しかもやさしくて紳士的なお客さん。
これで今月はクレジットカード1枚分の支払いができる。おなじことをあと何回やれば、4枚すべてのカードの支払いができるか、わたしはその瞬間計算してしまった。
「うちのお店は前金制だから、プレイ前にお客様からお代をいただいてください」ってお店の人に言われていたけれど、営業職なんてしたことのないわたしは、どうやって前金をいただけばいいのか、ずっと悩んでいたのだ。「お金、ください」って、ふつうの女の子が言える? 今回は優しい人だからよかったけれど、早く慣れていかなくちゃ。
彼が先にお金を用意してくれていたおかげで、私の笑顔は営業スマイルから、徐々に普段のスマイルへと変化していった。
それでも、初めてお客さんの前で洋服を脱いでハダカになるときは、心臓が口から出そうだった。しかしいちどハダカになってしまうと、なぜか心は落ち着いた。
お客さんにうながされるまま、シャワーを浴び、浴室から出ると、彼は部屋の照明を少し落としてくれていた。
「このくらいの明るさで大丈夫?」とお客さんは言った。
「はい」と私はうなずいた。お礼を言おうとしたけれど、恥ずかしくて言えなかった。
わたしは、彼の女性に対する気遣いに、純粋に感謝した。
お客さんに手を引かれてベッドに入ったとき、自分でも全身がガチガチになっているのがよくわかった。私は目を閉じてあおむけに寝たまま、お客さんに身をまかせた。お客さんがわたしの緊張をほぐそうと努力してくれているのが、全身から伝わってくる。そしてわたしとおなじように、お客さんも緊張しているのがわかった。
お客さんの方も緊張するんだ……わたしにとって新しい発見だった。でも、そりゃそうだよね、と思った。若い女の子のハダカを見て緊張しない男性は、おそらく少数派だろう。
彼の愛撫は、これまで付き合ってきたどの元カレよりもやさしく、かつ激しかった。
イキやすいわたしは、すぐに果てた。
お腹を小さくヒクヒクさせているわたしに、彼は薄い布団をそっとかけながら言った。「気持ちよかった?」
わたしが彼の目をみてうなずくと、彼はわたしの頭を撫でて安心したようすだった。彼はわたしの横にあおむけになって寝ころび、わたしの年齢や昼間の仕事について尋ねてきた。
「ポスト屋さん」私が言うと、
「ポスト屋?」と彼にはピンとこないようで、何度か同じ言葉を口にして笑った。
わたしの昼間の仕事は、本当にポスト屋さんだった。マンションのエントランスにある、細長いシルバーの集合郵便ポストを、住宅メーカーやホームセンターなどに卸している会社の営業事務をしているのだ。そんな会社、社名でも言わない限り、だれも知らない。
「新しくマンションやアパートをつくるときに、ポストの注文がくるの。シルバーの郵便ポストを100個くださいとか。わたしは見積書をつくったり、請求書をつくったりしてる」
「毎日毎日、郵便ポストって、たくさん売れるものなの?」彼は不思議そうにわたしに尋ねた。
「週に1,000個くらい売れたらマシなほう。だから仕事は暇なんだ。あとは、郵便ポストの暗証番号を忘れたから教えてほしいとか、マンションの管理人さんから問い合わせの電話があって、その電話も受けるんだ。でも、結局、1日8時間のうち3時間くらいは暇」
「暇なときってなにをしているの」彼はツルリとしているわたしのお腹を撫でながら言った。
「会社のパソコンで風俗の求人サイトを見てる」わたしはしれっと答えた。お客さんとベッドの上で話すという、初めての経験にすこし慣れてきたのかもしれない。
彼は納得したように言った。「それはいいことだよ、時は金なりって言うしね、若いうちにいっぱい風俗で稼いでおくのもひとつの手だ。貯金したり旅行に行ったり資格をとったりすれば、人生の幅も広がる」
風俗嬢に人生を語る男……なにものなんだろう? わたしはお客さんに、どんな仕事をしているのか聞いてみた。
「おれ? おれは不動産の会社を経営しているんだ。去年会社を立ち上げたばかりだから、まだそんなに儲かってはいないけど、90分で3万円くらいのお店でなら、週に1回くらいは遊べる」
その話を聞いて「わたしは運がいい」と思った。だからわたしは精一杯のこころをこめて、風俗業界未経験で、右も左もよくわからないけど、よろしくお願いしますと彼に言った。
「もちろん」と彼は言って、またわたしの頭を撫でた。
それからシックスナインをしたり、フェラをしたり、わたしが彼の乳首を舐めながらアソコをしごいてあげたりした。彼はわたしがなにをしてあげても、うれしそうだった。
素股でフィニッシュしたあと、彼はわたしにありがとうと言った。「優子ちゃんも、イカせてあげようか? シャワーを浴びる時間とか、着替える時間を考慮しても、あと30分くらい時間が残っているから」
それから30分、彼はみっちりとプレイを続けて、ホテルの部屋を出るとき、「また指名するから遊んでね」とわたしに言った。
わたしは彼の手を握って「今日はありがとうございました」と言い、そっと扉を閉めた。
*
わたしは運が良かったのだろう。
風俗バイト初日のお客さんはやさしく、しかも少々お金持ちで、プレイ内容は紳士的だった。それにお金をいただきながら、わたしもイクことができた。
お金をもらいつつイクというのは、なんとも不思議な感覚だった。
もちろん、好きな彼氏とするセックスとは違う。
でも、やっぱりというかなんというか、女の子にだって性欲はあるわけだし、わたしのように彼氏と別れて半年もセックスをしていないとなると、お客さんとの前戯や素股に、ある種の納得感が生まれる。元カレよりも紳士的にかつ激しく、何回もイカせてくれたらなおさら。
結局、その週の金曜から、わたしは週3で歌舞伎町のデリヘルでアルバイトをすることにした。待機所の近所のホテルに呼び出されることもあれば、送りドライバーが指定場所まで送ってくれることもあった。
どこでどんなエッチなお仕事をしても、多くの場合、わたしには納得感があったし、出勤するたびに、肉体的な納得感を上まわるお給料を手にすることができた。
でも、この仕事をはじめて数ヶ月がたって、秋風が冷たくなりはじめた頃、わたしはお客さんとの“気持ちよさの交換ごっこ”に物足りなさを感じるようにもなった。辛いとかそういう感情ではない。お客さんに痛いことをされるわけでもないし、お金を払ってくれないお客さんがいるわけでもない。思っていたよりずっとふつうのサービス業なのだ。
でもわたしにはさらなる欲がわいてきて、だれかにもっとわたしのことを必要とされたいと思うようになった。
リピーターになってくれたお客さんのことを好きになりかけたことだってあった。
でも仕事は仕事だ。
リピートしてくれるお客さんは、憧れの目でわたしのことを見ている。憧れる側と、憧れられる側は、まったくちがうことを考えている。ちょうどマジシャンと、マジックを見ている人の気持ちのように。アイドルと、アイドルの追っかけをしている子のように。
ああ、もっとだれかに、本当のわたしを必要としてもらいたい。
わたしが歌舞伎町にハマったのは、この年の11月のことだった。ホストなんて女を騙すだけのろくでもない生き物……こうは思っても、いちど通い始めてしまうと、手が勝手にスマホでホストクラブをググりはじめ、足がひとりでにホストクラブに向かうのだから、しかたない。
朝10時に渋谷のポスト屋に行き、18時に退社する。その足で歌舞伎町のデリヘルの待機所に向かい(だいたい2時間待機(仮眠)、4時間労働、1時間移動というかんじだった)、深夜の2時にバイトを終え、そこから歌舞伎町のホストクラブに行く……火曜と木曜と金曜はかならず行く――こういうスケジュールになった。
ホストクラブに行くと、20歳そこそこの若くてかわいいホストたちが、わたしのことをちやほやしてくれた。彼らはきまってお腹をすかせていた。
わたしだってお腹をすかせている。歌舞伎町のデリヘルでそれなりのお給料をいただいているものの、今でも買い物癖がなおることはなく、クレジットカードの支払いに追われ、ホストクラブに支払うお金も必要になり、結局、昼ごはんはコンビニのおにぎり1つとか、夜ごはんはデリヘルの待機所でカップラーメンをすするだけとか……。
でも若くてかわいい新人ホストは、わたし以上に貧しそうだった。裾がほつれた黒いズボンに、今にも穴が開きそうな黒い靴を履いていた。
だからわたしは眠たいのを我慢しつつ、ホストに求められるままホストクラブに通い、飲まない高級な酒のボトルを入れ続けた(わたしはお酒が飲めないから、いつも、どんなお酒もホストに飲ませてあげていた)。ホストがスーツがほしいと言えば、スーツ代だって渡してあげた。
気がつくと、わたしのクレジットカードの利用残高は歌舞伎町で風俗バイトをする前と比べ、さほど減っていなかった。
利用可能額は毎月1,000円とか、そういうしょぼい金額だった。
利用限度額が増えた分、わたしが気前よくカードを使ったからだ。
そしてホストクラブへのツケは150万円になっていた。
「なあ、優子」とホストは私の肩をさわる。「優子がバイトしている歌舞伎町のデリヘルの**ってさ、うちのホストクラブのオーナーの知り合いのお店だからさ、優子、お店の幹部に信用されてるよ。だからさ、今夜も飲み代、ツケにしておくから、お金が入ったら払ってよ、無理しなくていいんだよ、お金が入ったらでいいからさ」
デリヘルに来る客は、わたしの若い肉体を必要としていて、若くてかわいらしいホストは、わたしのお金を必要としていた。
だれかに必要とされていると思えば、自然と気持ちは高ぶり、理性を失った諭吉はわたしのもとにやってきては、すぐに消えていった。
息つく暇もないわたしの生活は、こうして幕が開いた。